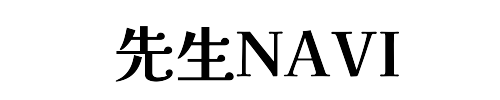教師の年金って、「年金払い退職給付」があるって聞いたけど、どんな年金?

複雑ですよね。でも、これはお得ですから知っておいたほうがいいですよ。
公務員の年金の3階部分、年金払い退職給付について、わかりやすくお伝えしますね。
公務員の年金については、こちらに詳しく書いてあります。
YouTubeでも解説しています。
厚生年金に上乗せされている部分
公的年金(国民年金・厚生年金)は 賦課方式という仕組みになっています。
賦課方式とは、給料から天引きされた掛金がストックされていくのではなく、
現在年金を必要としている人に回される仕組みです。高齢社会で心配されているのは、背景にこの方式が採用されているからかも。

銀行の預金が銀行にはなくて、
他の人に貸し出されている、といったイメージですね。
一方、「年金払い退職給付」は、
積立方式なので、ストックされていく仕組みです。
今のところ、確実に受け取ることができるイメージですね。
毎月いくら積立ているの
まずは給与明細をチェック
年金払い退職給付は、給与ランクに応じて積み立てていきます。
手元に給与明細があったら確認してみるといいですよ。

共済長期(退職等)と書かれている金額が、年金払い退職給付に関わってきます。
※ちなみに、
共済短期は健康保険
共済長期は年金保険になります。
このケースであれば、3,300円引かれているんだなと考えておけばいいです。
ですが、実際に積み上がっていく金額は少し違います。
7月に送られてくるはがきをチェック
毎年7月には、公立学校共済組合から「年金払い退職給付」に関するハガキが郵送されてきます。

中を開くと、これまでいくら積み上がっているかが確認できます。

例えば9月を見ると、、
給料に応じて標準月額(410,000円)が定められ、
付与率(下に書かれている1.500%)に応じた付与額(6,150円)と記載されています。
利息が付いている月もあります。
一番右側が、これまで自分で積み上げた残高です。
12月はボーナスも含まれるので、
それぞれの金額が上がっていることがわかります。
毎月給与から惹かれる金額(3,300円)と、
年金として積み上げられる金額は倍ほど違います。
これは、所属先が半分負担してくれるからです。
ちなみに、公務員在職中は、このハガキは毎年届いているはず。
公務員を辞めた場合は、35歳、45歳、59歳の節目の年齢の翌年に届くようになっています。
年金払い退職給付の受け取り方2種類ある
受給できるのは原則65歳からですが、退職しないと受給することはできません。
65歳以降、再任用などで、正規雇用と同様の状況が続くときは受給できないのでご注意ください。
積み上がった年金払い退職給付の算定金は、半分に分けてて2通りで受給する
積み上がった金額は、半分を①有期退職年金として、もう半分を②終身退職年金として受け取ります。
例えば、40歳〜60歳までの20年間で、250万円積み上がった場合は、
125万円 → 有期退職年金
125万円 → 終身退職年金
として受け取ります。
①有期退職年金
期間を分けて受け取る方法です。
・20年で分割して受け取る
・10年で分割して受け取る
・一括で受け取る
分割して受け取る場合は、
「積み上がった残高 ÷ 有期年金原価率」で計算します。
※有期年金原価率は、ハガキに書かれています。
私が確認したハガキでは、20年分割:20.0000、10年分割:10.0000と書かれていました。
ですので、20年分割の場合、
(20年分割)
125万円 ÷ 20.000 = 62,500円
62,500円 ÷ 12ヶ月 = 5,208円
(10年分割)
125万円 ÷ 10.000 = 12.5万円
12.5万円 ÷ 12ヶ月 = 10,416円
が、毎月の年金に追加されます。
途中で年金受給者が亡くなった場合は、
残りを遺族が一括で受け取ることになります。
②終身退職年金
こちらも
「積み上がった残高 ÷ 終身年金原価率」で計算します。
※終身年金原価率は、23.0337474です(変更の可能性あり)
ですので、
125万円 ÷ 23.033747 = 54,268円
54,268円 ÷ 12ヶ月 = 4,522円
このケースの場合、年金払い退職給付が月に約1万円程度年金が上乗せされることになります。
終身退職年金は、本人が亡くなってしまうと受給は終了になります。
まとめ
いかがでしたか。
共済年金が厚生年金に統一されましたが、
「年金払い退職給付」によって公務員の年金は手厚い部分が残っています。
ぜひ、手紙が届いたときにはすぐに捨ててしまわずに、
内容を確認してくださいね。
年金についてはこちらの記事も参考になります。
☆厚生年金が一部カット⁉
☆ありがたい遺族年金の仕組み