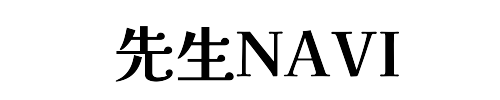「毎月の給料では、なかなか貯金ができない…」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
20代のときには、給料と労働の釣り合いが取れなくて、その少なさに疲弊していました…。
若い公務員の方が、仕事内容と給与のバランスが合わずに退職していくこともあります。
公務員の場合、収入を増やすことは難しいので、
まずは支出を抑える「節約」から取り組んでみませんか。
明日からできる公務員の節約法6選をまとめました。
①支出を把握する
②口座を分ける
③格安SIMに変える
④自動車保険の見直し
⑤家賃を下げる
⑥もともと安いものを買わない。安くなっているものを買う。
1.支出を把握する
「あれ?どこにお金が消えているんだろう…」
お金は減っているのに、何に使っているかわからないことってありませんか?
貯蓄が苦手な人は、毎月の収入以上に支出が多く、
月々のマイナス分をボーナスで補填する傾向が強いです。
ここから抜け出すには、「支出を把握すること」から始めることをおすすめします。
支出を把握する方法 電子マネーとクレジットカード
「それはわかっているんだけど、めんどくさい」
「家計簿を書くなんて、そんな細かいことはできない」
「レシートを取っておくのがめんどう」
ですよね。ちょっとしたひと手間ができないんです。だから、やってもらいましょう。
支出だけに絞って、自動的に記録するんです。
自動的に記録するようにしないと、手書きするとか、PCから入力なんて、続きません。
①電子マネーを利用する
②クレジットカードで支払う
こうすると、使った痕跡が自動的に残るので、毎月どのくらいのお金がかかっているかがわかります。
支出総額より、各項目にいくら使ったのかを把握すると、
翌月の対策ができます。
「余計な支出だった」と反省して次の行動に繋げられるのです。
絶対に支払わないといけない金額は、電子マネーやクレジットカードを使いましょう。
・何に使ったかの爪痕が残る
・ポイントがもらえる
という2つのメリットも一緒についてきます。
家計簿アプリの利用もいろんなところで言われていますが、
最初の設定で挫折することが多いです…
ですので、節約・貯蓄したい人は、クレジットカードや電子マネーを使うことをおすすめします。
口座を分ける
給与が振り込まれる口座、
まさか、1つではないですよね⁉
という私も、元々は1つでした(おい!)
実はこれ、お金が貯まらない典型的なパターンです。
特に、ボーナスまで同じ口座に入るようにしていた場合は悲惨なことに。
月々のマイナスを、ボーナスで補填する。
年に2回のボーナスは、
日々の赤字を補うためのものになると、
貯金はできません!
というわけで、口座は3つに分けて管理しましょう。
①貯める口座(まずは生活費の半年分を目指す)
②支払う口座(公共料金等)
③使う口座(プライベートな出費)
①貯める口座
・月々の手取りの◯%
・ボーナス
などが自動的に振り込まれる口座です。
万が一にや将来の安心に備えて、
「先取り貯金」をしていきましょう。
まずは手取りの10%から始めることをおすすめします。
貯める口座は利便性よりも、利率の高さで選びましょう。
引き出すことは少ないはずですから、
メガバンクや地銀の普通口座は除外して、
利率の高い銀行などを選んでいきましょう。
②支払う口座
ここには、公共料金や家賃・通信費などの生活費を把握した上で、給与を振り分けていきます。
・自宅のインターネット使用料 6,000円
・光熱費(電気代・水道代) 23,000円
・電話やケーブルテレビ 5,000円
・スマホ2代 4,600円
クレジットカードや電子マネーで支払うことで、月に約40,000円程度かかると把握できます。
次に、この口座には毎月給与のうち40,000円を振り分けておきます。
カード支払いの場合は事前に通知が来るはずですから、不足する場合は入金します。
③使う口座(プライベートな出費)
個人的な買い物、お付き合いなどに使う口座です。
たくさんお金を残しておくと、「消費」ではなく「浪費」の元になるので、多額を置かないようにしましょう。
③の口座用にも、クレジットカードを用意するのがおすすめ。
クレジットカードを1枚にしたほうがポイントが増えますが、
カードと紐づけできる口座の数は1つです。
ポイントよりも、まずは何にどれだけ使っているかを把握することが大事だと考えます。
②や③の口座で余りが出たら、すぐに①の口座へと移していきましょう。
余ったお金をそのままにしておくと、
次の月に使ってしまうからです。
支出は収入まで膨らんでしまう。お金と時間はあるだけ使ってしまう傾向が強い。
給与という収入を分散し、口座に残るお金を少なくすることで、
無駄な出費を減らし、貯める口座の数字は着々と増えていきます。
「自分は貯蓄ができるんだ」と自信につながるんです。
しかし、節約のやり過ぎもストレスになりますから、
たまには自分へのご褒美も忘れずに用意したいですね。
格安SIMに変える
毎月のスマホ代はいくらかかっていますか?
5,000円以上かかっているのであれば、最優先で見直しをしたい項目です。
月5000円であれば、年間55,000円。
それが月3,000円に下がれば、年間19,000円節約できます。
通信・端末・決済などモバイル分野で国内最大規模の調査を実施しているMMD研究所(モバイルマーケティングデータ研究所)によると、
月々の携帯料金(通信+通話+端末)の支払いは、
3大キャリアは9,498円
格安SIMの場合は4,258円となっています。
端末を除いた通信+通話の場合は
3大キャリア…5,151円
格安SIM…1,634円
と、その差は歴然。
スマホは必需品ですが、ハイスペックなものが必要でしょうか。
3大キャリアは車でいうと言わば「高級車」
出費を抑えるためには、まずは格安SIMという普通車に変えてみませんか。
自動車保険の見直し
自動車を所有する場合は、任意保険が必須ですね。
年間いくら支払っていますか?
毎月の支払いだと、一括よりも増えてしまう。
でも、一括で払うと多額になる。
若い場合は等級も低いので、保険料は上がってしまいますよね。
一人1台所有する場合は、なおのこと負担大です。
皆さんは、自動車保険はどこで加入していますか?
私の場合は、
親が加入していた保険会社 → 全労済 → お世話になっている車屋さんにお任せという流れをたどりました。
等級が上がったのに2台で15万円。(しかも1台は軽自動車)
そこで、ネットで自動車保険の見積もりを取ると、
2台で6万円程度に。
「自動車保険は車屋さんに任せていれば大丈夫」と思っていたので、
目からウロコでした。
ネット割引なども適応されるので、
一度見積もりを取ってみると良いと思います。
ちなみに私が使っているのはソニー損保です。
家賃を下げる
一般的には、教員は上限28,000円まで住宅手当を支給してもらえます。(賃貸の場合。持ち家はない)
しかし、生活費の中で家賃の支払いがあるということは、付随して光熱費の支払いもあるということです。28,000円の支給を受けても、残りの28,000円の支払いだけでは済みません。電気代や水道代、ガス代、電話代…多くの出費がかさむ原因になるのが、一人暮らしや賃貸で住まうことです。
可能なら、実家で生活することをおすすめします。
食費や洗濯の費用、それにかける時間まで節約することができます。(自主的にご飯を作ったり洗濯することはいいことですが)
もともと安いものを買わない。安くなっているものを買う。
安物買いの銭失いを経験したことはありませんか?
「安い物は品質が劣るから、結局、高くつく」という意味の言葉。日常のいろいろな場面で見られます。
値段は安い方が家計にはありがたいですが、すぐ傷んでしまったり、洗濯に耐えられなかったりして、結局買い直すことになれば、費用がかさんでしまいます。 商品の代金だけでなく、お店に行くための交通費や時間もかかってきますね。
例えば衣料品。
「このシャツは安い!元値が1000円!」
つい買いたくなりますよね。
値段に飛びついて購入したものの、すぐによれてしまう。
高い衣料品を購入すると出費がかさんでしまいますが、
もともとは高い服が安くなっている場合に購入すると、
高品質なものを低価格で手に入れることができます。
食品の場合も同じことが起こるのではないでしょうか。
あまりにも安価な食品は、味はいまいち…なんてことはよくある話。
食品も、ある程度はお金をかけないと、日々の生活の中で貧しさを感じるようになります。しかし、賞味期限が近づいた商品が安く売られている場合は別だと思うのです。
賞味期限が近いだけで、健康を害するものではありません。安く美味しくいただけるので、私は買い物の際に積極的に見切り品コーナーを除いて、必要なものがないか選んでいます。
ただし、セールに行こうと言っているわけではありません。
セールでは、安さに魅了されて、必要のないものまで「ついで買い」してしまうので、節約どころか浪費になってしまいます。浪費が激しい場合は、ものに近づかないことが一番です。
・必要な物、質の良いものをできるだけ安く購入する。
・良いものを長く使う。
・美味しいものを、美味しくいただく。
高価なものを買わなくても、日々の生活は潤うんですよね\(^o^)/